権威ある新しい教え(マルコ1:21-28)20240519
- 金森一雄

- 2024年5月19日
- 読了時間: 9分
更新日:2025年5月20日
本稿は、日本基督教団杵築教会におけるペンテコステの2024年5月19日聖霊降臨節第1主日礼拝の説教要旨です。杵築教会伝道師金森一雄
(聖書)
コヘレトの言葉12章9~14節
マルコによる福音書 1章 21節~28節
(説教)
1.ペンテコステ/聖霊降臨日
今日はペンテコステ/聖霊降臨日です。聖霊降臨日の出来事は、聖書の使徒言行録2章に記されています。ペンテコステという名前はギリシャ語の「50番目」を意味する言葉です。主イエスが天に上げられた50日後の、ユダヤ教の7週の祭りの出来事です。地上に残された弟子たちに聖霊が注がれました。弟子たちによって神の言葉が語られ、その言葉が聴かれ、聴いた者たちの中から、信じて、3000人ほどの洗礼を受ける者たちが起こされました(使徒2:41)。ヨハネによる福音書14章16節に記されている、弁護者を遣わしてくださるという約束の成就の出来事です。弁護者( παράκλητος )とは、助け手とかHelperと訳されますが、この出来事によって、多くの信仰者が生まれ、教会生活が始まり、ここに教会が誕生したのです。ですから、ペンテコステは、教会の誕生日とも言われている日です。
杵築教会は、1888年に大分尋常中学校の教師として来日したS・H・ウェンライト師が、最初に導いた中根中氏を郷里伝道として、1889年11月1日に杵築に遣わした、その日を創立記念日としています。そして今があります。それも聖霊の業、不思議です。
使徒言行録2章の二千年以上前のエルサレムの初代教会の出来事も不思議です。今もなお、すべての教会に、聖霊が憐れみと恵みをもって、わたしたちを慰め、導き続けてくださっています。
わたしたち杵築教会では、この2024年4月から、マルコによる福音書の連続講解説教が続けられています。主の計らいには驚くことばかりです。今日も、ペンテコステの説教箇所として、ふさわしい聖書箇所が与えられました。主なる三位一体の神様に感謝しています。
2.イエスの教え
マルコによる福音書の1章21、22節には、「一行はカファルナウムに着いた。イエスは、安息日に会堂に入って教え始められた。人々はその教えに非常に驚いた。律法学者のようにではなく、権威ある者としてお教えになったからである。」と記されています。
21節の冒頭で「一行」と記していますが、一行とは、主イエスと、ガリラヤ湖で主イエスに従ったシモン、アンデレ、ヤコブ、ヨハネの4人の漁師たちのことです。
カファルナウムは、ガリラヤ湖北岸の交通の要衝で、ユダヤ教の立派な会堂がありました。今も聖書旅行の観光地として多くの人を集めています。主イエスの最初の弟子となったシモンとアンデレが住んでいた家がありました。そして、主イエスの公生涯の宣教活動において、もっとも重要な伝道の本拠地(ベースキャンプ)になっていく所です。
聖書の原典では、21節の「カファルナウムに着いた。」と「安息日に会堂に入って教え始められた。」という二つの文章の間にεὐθὺς「そのとき(すぐに)」という言葉があります。「そのとき」という言葉は、新共同訳聖書では訳出していません。マルコは、主イエスがカファルナウムに入って、すぐの安息日に会堂に入って教え始められたと強調しています。
なぜ、そんなに主イエスは急がれたのでしょうか?実は、大切なメッセージがありました。
15節で、主イエスは「時は満ち、神の国は近づいた。」と宣言されています。
ですから、ぐずぐずしてはいられません。私たちが考えるような、いろいろ準備をして段取りや体制を整えてから、というのではないのです。主イエスと4人の弟子の一行がカファルナウムに着くと、すぐの安息日に会堂で教えることによって伝道を始めたというのです。
会堂は、シナゴーグといいます。「集まり」という意味です。
ユダヤ人たちは、エルサレム神殿が破壊されてからは、シナゴーグにおいて律法を学ぶ集まりをユダヤ人たちにとって唯一の神様を礼拝する場として、礼拝を行っていました。
主イエスはユダヤ教の人々が集まって神様を礼拝している会堂に行かれました。ですから、このユダヤ教の安息日の礼拝が、キリスト教会の日曜日の礼拝の起源となったのです。
その時に教え始めたことの詳細につては、マルコは記していません。
マタイによる福音書は、マルコより後に執筆された福音書ですが、その時のイエスの教えの詳細を「山上の説教」(マタイ5章)として記しています。その一連の説教の終わりとなる7章28、29節に、「山上の説教」を総括する言葉が記されています。
「イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆は非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、権威ある者としてお教えになったからである。」というものです。
お気づきになられた方もいらっしゃるようですね。
マルコによる福音書1章22節の言葉「人々はその教えに非常に驚いた。律法学者のようにではなく、権威ある者としてお教えになったからである。」というのは、マタイ7章28節の「山上の説教」の総括の言葉で、ほぼそのまま用いられています。マタイは、マルコが記していない権威ある教えの詳細は「山上の説教」ですよ、と言わんばかりなのです。
3.汚れた霊との戦い
23節の冒頭にも、マルコの文態の特徴である、「そのとき(すぐに)」(εὐθὺς)という言葉を記しています。汚れた霊に取りつかれた男のいやしの出来事を、同じ安息日に同じ会堂で起こった出来事として、連続して記述しているのです。
24節で、汚れた霊に取りつかれた男は、「ナザレのイエス、かまわないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ」と叫びました。この男の叫びの言葉に何か引っかかりを感じませんか。その男は、イエスを知っています。出身地がナザレだということまで知っていました。そして、「かまわないでくれ。」「我々を滅ぼしに来たのか。」「正体は分かっている。神の聖者だ。」と、イエスの力までしっかり知っているのです。
ここの「かまわないでくれ」という言葉は、口語訳聖書では、「あなたはわたしたちとなんの係わりがあるのです」と、翻訳されています。こちらの方が原文に忠実な翻訳です。
「お前は我々と何の関係もないだろう」ということです。「係わり合いになりたくない」という意思を示しますから、新共同訳が「かまわないでくれ」というのは、的を得ています。
要は、かまって欲しくない、ほっといてくれ、とこの男は言っているのです。
さらにこの男が「我々を滅ぼしに来たのか。」と語っています。この男に取り憑いた複数の汚れた悪霊が「我々」という複数形を主語にして語っているのです。この男は、心がいくつにも分裂して、人として心身の統合ができなくなっているようです。最近までは、汚れた霊は、人間に取りつき、様々な病気、特に心の病を引き起こすものと考えられていました。
病気になって別人のようになって、肉体が汚れた霊に乗っ取られて悪魔の言葉を語るようになっている、と考えられたのです。現在は医学が進んで、統合失調症といわれています。
心の病気の人を悪魔祓いと称して排斥することはなくなり、適切な治療をしています。
だからと言って、悪霊は昔の無知の産物だと判断するのは軽卒に過ぎます。
汚れた霊は、病気とは関係なく今もこの世界の闇の中で力を奮っています。
神様よりも自分の思い、考え、願いを第一とするようになり、それに反対して自分を妨げる者に対しては、敵だと見なして、人間が互いに傷付け合うような悲惨な対立を生みます。
国と国との戦争や、民族の対立、むごたらしい虐殺や迫害がそれです。
私たちは、汚れた霊の働きを決してあなどってはなりません。むしろ今の社会において、汚れた霊の脅威があり、汚れた霊が私たちから何を奮おうとするのか、汚れた霊に取りつかれることによって何が起っているのかと、しっかり受け止めておく必要があります。
25節で、主イエスは、「黙れ。この人から出て行け」と汚れた霊をお叱りになりました。
すると悪霊は出て行きました。主イエスは、み言葉で悪霊に勝利し、悪霊に取りつかれている人をその支配から解放して下さいました。
27節で「人々は皆驚いて、論じ合った。『これはいったいどういうことなのだ。権威ある新しい教えだ。この人が汚れた霊に命じると、その言うことを聴く。』」と記されています。
ここの「皆驚いた」というのは、ギリシャ語では非常に大きな畏れを伴う驚きを表す言葉θαμβέωが用いられています。22節で用いられた、驚いたἐκπλήσσω(amaze)とは異なり、27節の驚いたというのは、恐怖の恐れではなく、本当にここに神がおられる、神が生きて働いておられるという畏怖(いふ)の念を持ち、畏れかしこまるという驚きを意味します。
ユダヤ人たちは、律法学者たちの教えをいつも聞いていました。
律法学者たちが、律法にしっかり根ざし、その正しい解釈が語られているなら、彼らの教えも権威あるものとなります。しかしその権威は律法の権威で彼らの権威ではありません。
彼らの勧めは、聴いてすぐに実行できるような教え、つまり倫理的、道徳的な教えで具体的で分かりやすいものです。しかし聴いている側に驚きはありません。私たちが既に知っていることですから、すぐにそうだなと思えるのです。
それに対して主イエスが「権威ある者として教えている」というのは、主なる神様ご自身が権威を持っておられる方として教えているということです。
主イエスの汚れた霊との戦いは、主イエスの十字架の死にまで至る戦いです。主イエスの神の子としての権威は、十字架の死において、そして父なる神様がその主イエスを死者の中から復活させ、永遠の命を生きる新しい体を与えて下さったことにあります。神様がその独り子イエス・キリストを遣わして下さり、その十字架の死と復活によって、私たちを罪の支配から解放し、神の子として生きる新しい命を与えて下さいました。ここに主イエスの神の独り子としての権威が示されているのです。
ですから、28節で、「イエスの評判は、たちまちガリラヤ地方の隅々にまで広まった。」というのです。主イエスの評判を誰が伝えたのでしょう。この出来事を目の当たりにしていた人々であり、そして何よりもこの男自身だったのでしょう。そしてガリラヤの隅々にまで主イエス・キリストの伝道が広まっていったのです。
私たちの信仰は、主イエスの生涯全体を驚きをもって見つめることから始まります。
そこには、私たちの倫理道徳の教えからでは決して得られないものがあります。
それは、私たちを悔い改めさせ、神様の救いの恵みに与る「権威ある新しい教え」です。
本日朗読していただいた旧約聖書のコヘレト(旧1048頁)とは、伝道者という意味です。
コヘレトは知識を深めるにつれて、より良く民を教え、知識を与えました(コヘ12:9)。
しかし、「書物はいくら記してもきりがない。学びすぎれば体が疲れる。」(コヘ12:12)と語り、12章13節の最後の言葉で、「すべてに耳を傾けて得た結論。『神を畏れ、その戒めを守れ。』これこそ、人間のすべて。」と記しています。
コヘレトは、神にこそ、権威があることを悟ったのです。
今日は、ペンテコステの日です。使徒言行録の2章に記されているペンテコステの出来事において、その日に三千人もの人たちが洗礼(バプテスマ)を受けた(使徒2:41)というのです。この数字も驚きです。この人たちは皆、何よりも主イエスの権威に驚いた人たちです。
その権威に驚き、信仰を持ち、教会が生まれたのです。
そして今も、多くの者たちが主イエスの権威に驚くのです。
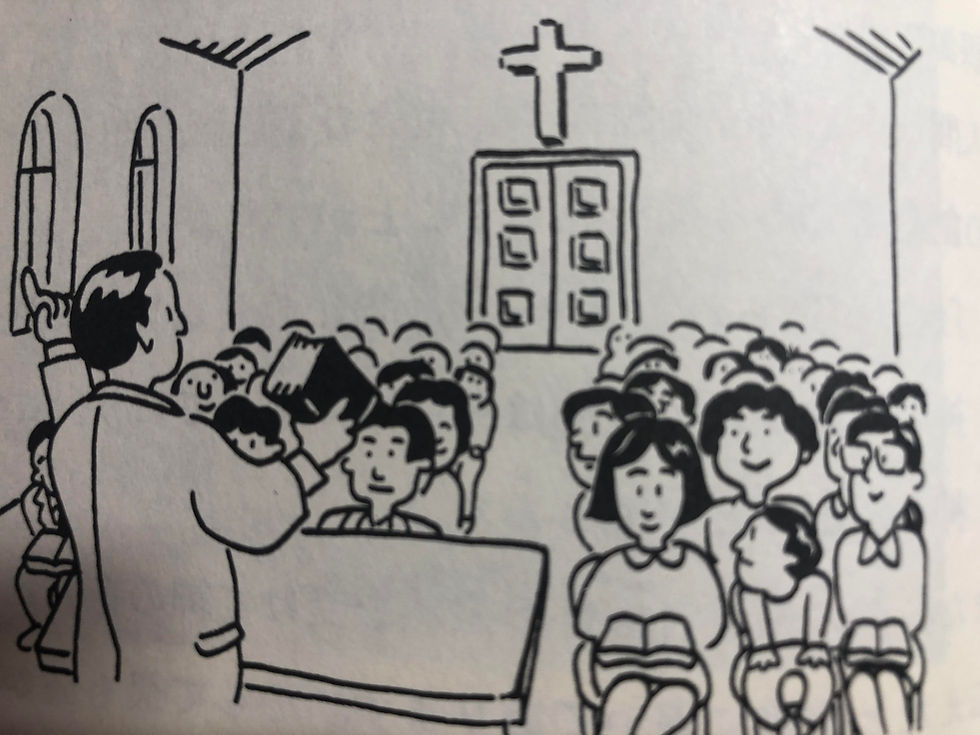
.jpg)

.jpg)
.jpg)









コメント