幻を見る(使徒15:36-16:10)20231022
- 金森一雄

- 2023年10月22日
- 読了時間: 14分
更新日:2025年5月21日

本稿は、2023 年 10 月 22 日(日)に中渋谷教会において行った、23 年度神学校日の説教を要約したものです。
旧約聖書:ヨエル書3:1(p.1425)
新約聖書:使徒言行録15:36-16:10(P.244)
(祈り)
主イエス・キリストの父なる神さま。
今、わたしたちは共に御言葉を聞きました。
あなたの御前で共に頭を垂れている一人一人を祝福してください。
そして、わたしたちに聖霊を注いで、
御言葉を悟らせてください。
主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。

1.はじめに
ただ今お読みした旧約聖書ヨエル書 第3章には、「神の霊の降臨」という小見出しがつけられて、わたし、すなわち主が、「すべての人にわが霊を注ぐ。」、息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。と記されています。
新約聖書においては、使徒言行録の2章に、聖霊降臨の出来事が記されていますが、そのときのペトロ説教において、「悔い改めなさい。めいめい、イエス・キリストの名によって洗礼(バプテスマ)を受け、罪を赦していただきなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。」と、福音の言葉が語られています。そして、何と、その日に洗礼(バプテスマ)を受けた人の数は、3千人ほどであったという、驚くべき、聖霊の働きが記されているのです。
本日は、こうした聖霊の働きを取り上げてみたいと思います。
パウロの第二次宣教旅行において、神の霊がパウロにどのように働きかけ、導かれたのかについて、御言葉からご一緒に聞かせていただきます。
2.パウロに示された神の霊―聖霊とイエスの霊と幻
(1)第二次宣教旅行
先ほどお読みした、使徒言行録15章36節では、パウロが「前に主の言葉を宣べ伝えたすべての町へもう一度行って兄弟たちを訪問し、どのようにしているかを見て来ようではないか」と、第二次宣教旅行の提言をしています。パウロは、第一次宣教旅行でいった町を再び訪問して、その後の各地の人々の安否を尋ねる計画を考えていました。
しかし、この宣教旅行では、はじめからその計画変更が生じています。
この宣教旅行が、前回訪れた町への再訪問が目的だとするならば、使徒言行録 13 章 4節に記されているように、アンティオキアからセレウキアの港にくだって、キプロス島に向けて船出するはずです。
第二次宣教旅行の出発にあたって、バルナとパウロの二人は、マルコを助手にするかどうかで意見が激しく衝突しました(使15:39)。宣教チームのリーダーである、バルナバとパウロの意見の衝突とは、何とも物騒な表現です。表面的な見方をすれば、教会の一致を妨げるような出来事と思えるようなことが起こったのです。彼らは別行動をとることになりました。バルナバは、マルコを連れて、第一次宣教旅行と同じく、キプロス島㊟1へ向かって船出していきました。 一方、パウロは、先にエルサレムから一緒にアンティオキアに派遣されていたシラスを、バルナバに代わる同行者として選びました。交通手段も前回とは異なります。船によらず、陸路での出発です。
㊟1:バルナバとマルコは従兄弟。キプロス島はバルナバの出身地。 (コロサイ書4:10)
バルナバ:本名ヨセフ、レビ族の出身、キプロス島生まれのユダヤ人。彼は財産をすべて売り払って、その代金を使徒たちに差し出した(使4:36)。 迫害者サウロ(パウロ)が回心すると、バルナバはすすんでこれを受け入れ、タルソスへ送り(使9:30)、後にアンティオキアに連れ帰った(使11:26)。 パウロの第一回の宣教旅行の同行者となってキプロスから小アジア(現トルコ)をめぐったが、第二回宣教旅行にあたってマルコとよばれたヨハネの同行の是非をめぐって、パウロと議論になり、別行動でキプロスへ赴いた(使15:39)。
バルナバとパウロの宣教への熱意が高じた議論や意見の衝突が起きたことについては、案ずることはなかったようです。
後にパウロは、聖書の中で、バルナバやマルコの名前をあげて、好意的な記述をしています。 第一コリントの9章6節では、パウロが使徒の権利について主張していますが、その中で、「わたしとバルナバ」といって、自分たち二人を同じ宣教者として並べています。
また、フィレモンへの手紙の24節の結びの言葉のなかでは、パウロが、「わたしの協力者たち」といって、4人の名前をあげていますが、その筆頭にマルコの名を記しているのです。
現に、神はパウロに、バルナバに代わる同行者としてシラスを与え(使15:41)、第一次宣教旅行で行ったデルベ、リストラでは、信仰によるまことの子テモテ(Ⅰテモテ1:1)を助手として加えてくださいました(使16:3)。
そして、パウロの一行は、「律法によらず信仰のみ」、「(異邦人に)重荷を負わせない」という、エルサレムの使徒と長老たちが決めた規定を守るようにと、人々に伝え(使16:4)はじめたのです。使徒言行録15章5節には、「こうして、教会は信仰を強められ、日ごとに人数が増えていった」と記されているのです。
ところで、もう一つ大事なことで、第二次宣教旅行と第一次宣教旅行とでは、異なることがあります。それは、宣教旅行の旅立ちにあたって「主の恵みに委ねられて」送り出されているかどうか、ということです。
「主の恵みに委ねる」とはどのようなことだと思われますか?
ギリシャ語の原典では、παραδίδωμιという言葉が用いられています。「引き渡す」hand overということを意味する言葉です。マルコによる福音書14章41節で、「時が来た。人の子は罪人たちの手に引き渡される」と主イエスが、ユダの裏切りによって、ご自身が「引き渡される」というときに用いられた言葉です。
宣教旅行の出発に当たっては、これからの道中でどのような苦難が待ち受けていても、彼らは神の恵みに引き渡されるのです。すなわち、神の主導のうちにあることとして、神の憐れみと恵みに委ねる、ということを意味する言葉として用いられているのです。
第一次宣教旅行でも、バルナバとパウロが「神の恵みに委ねられて」送り出されたと、同じπαραδίδωμιが用いられています(使14:26)。ところが、39節では、バルナバとマルコが出発した際に、「主の恵みに委ねられ」という記述がありません。一方、40節では、パウロとシラスが出発するにあたって、兄弟たちから「主の恵みに委ねられて」出発した、と記されています。
使徒言行録の執筆者であるルカは、「神の恵みに委ねられて」という言葉を記すかどうかによって、そのように送り出されたパウロとシラスの一行が、アンティオキア教会の支持を得た正当な宣教旅行であるということを印象付けているのです。そしてルカは、そのキーワードを持たない、バルナバとマルコの宣教旅行については、これ以降、使徒言行録では何も記していないのです。
(2)神の霊による計画変更
使徒言行録 16 章1節を御覧ください。
これからお話しする中では、多くの地名が出てきます。地図を必要とされる方は、聖書巻末の付録の「聖書地図8」を御覧ください。
先ほどお話したとおり、宣教旅行のチームが二手に分かれたからなのでしょうか、パウロは、陸路で、前回は足を踏み入れていないシリア州やキリキア州を回って諸教会を力づけました。そして、第一次宣教旅行で訪問していた、デルベ、リストラ、イコニオンまで行きました。ここでテモテが登場しています。彼は、父親がギリシャ人で母親がユダヤ人です。3節には、評判の良い人であったとあります。当時の習慣として、母親がユダヤ人であっても父親が異邦人の場合は、割礼を授けません。割礼を受けるには、本人の意思表示が必要です。パウロはテモテを助手にしたかったので、自分の手でテモテに割礼を授けたのです。
テモテはこれ以降、主の摂理の中で、伝道者として大きく用いられていきます。 後に、パウロはテモテのことを、第一テモテ1章2節で、「信仰によるまことの子テモテ」と最大限の愛を込めたことばを用いて表現しているのです。
6 節を御覧ください。パウロの一行は、アジア州で御言葉を語ることを聖霊によって禁じられました。当時のアジア州は、ローマ帝国の貿易ルートの交差点であり、民族的にも文化的にも多様性に富み、様々な教会形成が行われた地域です。ヨハネの黙示録2章に記されている、代表的な7つの教会は、すべてこの小アジアといわれる地域にあります。
このような点を勘案すると、ここでパウロが聖霊によって、アジア州で御言葉を語ることを禁じられたから、アジア州での宣教活動を中止した、と考えることには無理があります。聖霊から、アジア州の中心地であるエフェソへと、西に向かう道を進むことを禁じられた、そのため、パウロは、一旦立ち止って、宣教旅行の行程変更を余儀なくされた、と考える方が自然です。
このため7節では、エフェソに向かう道ではなく、北西に進む道を選択しています。
パウロの一行は、ガラテヤ、フリギア地方を通って行き、「ミシア」地方の近くまで行っいって、黒海に面する「ビティニア州」に入ろうと、何度も入ろうと試みました。 するとそこでは、「イエスの霊」㊟2がそれを許さなかったというのです。
㊟2:「イエスの霊」は、聖書の中で使徒言行録 16:6の一箇所だけで用いられている。
6節では「聖霊から禁じられた」、7節では「イエスの霊がそれを許さなかった」と、いうのですが、聖霊とイエスの霊ではどのような違いがあるのか、また、パウロにどのように具体的な働きかけがあったのか、ということについては聖書には記されていません。
「霊」という言葉は、ギリシャ語では、同じΠνεῦμα(プネウマ)が用いられています。精神(spirit)、風(wind)、息(breath)とも翻訳される言葉です。ここでは、文脈上、聖霊もイエスの霊も、同じ「神の霊」だと考えていただければよいと思います。 宣教旅行を続けることについて、何らかの形で、それはダメだと「神の霊」が働かれたのです。
「神の霊」が、パウロに禁じ手を示しました。おそらく一行の祈りの中で、その時パウロがしようとしていることに、神の霊から、No、ダメだと示されたのでしょう。註解書によっては、パウロが体調を崩して宣教旅行が難しくなっていたのではないかと、いう学者もいます。確かに、自分が計画したことについて、それは駄目だと、神からダメ出しを食らったのですから、普通の人間なら、いじけてしまって体調を壊したりするかもしれません。しかし、パウロは、逆戻りしていません。宣教旅行を中止してもいません。立ち止まりこそしましたが、二度とも計画を変更したのです。別の道を「通って行った」のです。
パウロは、このように忍耐強く、何度も行程変更を繰り返しながら進んでいきました。
パウロの伝道への情熱(passion)は、そんなにやわではありません。
そして、ようやくミシア地方を通ってトロアスに下ったのです(8節)。トロアスの対岸は、エーゲ海をはさんで、ヨーロッパのマケドニア州で、異教の地ギリシャです。
こうして神の霊が、神が必要とする所に、パウロの一行を導かれたのです。
3.ヨーロッパ宣教への神の招き
9節を御覧ください。トロアスに到着したその夜、パウロは「幻」を見ます。一人のマケドニア人が立って、「マケドニア州に渡って来て、わたしたちを助けてください」とパウロに懇願したのです。
パウロはマケドニア人の「幻」をおそらく夢で見たのでしょう。「幻」が、パウロに語りかけて、ヨーロッパの地、マケドニアへと招いたのです。今回は、ダメだとかNOといった禁止ではありません。神の霊によって、具体的かつ切実な招きが示されたのです。
ここに至り、一連の状況が大きく変わりました。
神の招きにより、異教の神に仕えていたギリシャ、マケドニア州への伝道が始められるのです。そして、神が必要とされた、厳しくとも、大切な、世界宣教の幕開けとなる出来事につながっていくのです。
10節では、パウロがこの幻を見たとき、『わたしたち』はすぐにマケドニアへ向けて出発することにしたと、エーゲ海を渡って、マケドニア州に向かう新たな行き先について、宣教チームの全員が、一致したことを強調して記しています。そして、マケドニアの人々に、神が福音を告げ知らせるために、神が『わたしたち』を召されていたと、確信したからである、と『わたしたち』という言葉を2度用いて、その理由を理路整然と記しているのです。
ここでいう、『わたしたち』とは、誰のことでしょうか。
使徒言行録を執筆した人は、ルカです。ここで、ルカ自身が、『わたしたち』の一人であると宣言するかのように、何の前触れもなく突然登場しているのです。
これ以降、使徒言行録16章11節以降、フィリピ滞在中の出来事について、執筆者のルカ自らが目撃した事を報告しているところは、『わたしたち』を用いて記しています。
ルカは、マケドニア人であり、トルコのアンティオキア出身の医者です。伝承によれば、パウロが医者と目薬を求めていたときに、ルカと出会ったようです。トロアスから一緒に、エーゲ海を渡りましたが、その後、フィリピで一旦、ルカは一行と別れています。そして、そのフィリピ滞在中に、クリスチャンになったと言われているのです。
神は、すべてのことを働かせて益としてくださいました。
憐れみに富み給う神は、大伝道者といわれるバルナバやパウロといえども、人間ですから自分の思いが先行して行動を起こすことがあることを神は御存知です。
そして神は、わたしたちを憐れんでくださり、神の霊によって導かれることを、わたしたちは知ることができるのです。
宣教のために献身するわたしたちは、御言葉と祈りによって、聖霊に満たされて、神の霊である幻や夢を見ることが大切です。そのため、わたしたちは、常に霊のアンテナを立てて、何事においても、御言葉を聞き、共に祈り、感謝して自分たちの歩みを振り返るのです。聖霊に導かれて計画を策定して、わたしたちが歩み出したからといって、御言葉を聞くことを軽んじてはなりません。途中でわたしたちにとっては、想定外の出来事が必ず起こるのです。主なる神は、そのことをも御存知なのです。
ピンチはチャンスの時。そのような時こそ、神の祝福に包まれる準備のときで、わたしたちは神のご意志と向き合うことになるのです。
インマヌエルの神、主イエスはわたしたちと共にいてくださいます。わたしたちは、主に従う僕として、礼拝から礼拝へと歩み続ける民なのです。
4.神とのコミュニケーション
中渋谷教会のルーツは、改革派の伝統の中に立っています。改革派の教会が大事にしてきた『ウエストミンスター信仰告白』第一章第一項には、「聖書を最も必要なものとしている」「神がその民にみ旨を啓示された昔の方法は、今では停止されている。」と、記されています。
その意味するところは、神が、神の意志と神の目的をわたしたちに啓示するに際に、過去においては、預言者を含む様々な手段を通して行っていましたが、現在は、御子イエス・キリストを通して、決定的かつ究極的な方法で語られた、ということです。すなわち、現在の神の啓示の主要な手段は、書かれた御言葉、すなわち聖書を通して行われると、イエスの果たす意義を強調しています。
本日の説教題を『幻を見る』としましたが、わたしたちは御言葉と祈りによって、聖霊に満たされて、神の霊である幻や夢を見ることが大切です。そのため、わたしたちは、何事においても、御言葉を聞き、共に祈り、計画を立てます。ところが、計画に沿って聖霊に導かれてわたしたちが歩み出したとしても、その途中で想定外の出来事が起こったりします。そして、イエスの霊がそれ以上の前進を許さず、立ち止まったり、向きを変えることが必要になるといった事態に陥ることも起こりかねないのです。
わたしたちにとって、途中で方向転換するということは、とても苦しい状況になっているということが予想されます。しかし、どのような状況になっても、都度、御言葉を聞き、祈りを伴う聖霊の働きにしたがうことが必要で、そのためには、聖霊が啓示していることについて、私たち信仰者の的確な識別と正しい解釈が求められます。また、 必要な助け手は、パウロにテモテやルカが与えられたように、都度、主が用意してくださっているのです。
わたしは、2020年の4月、コロナの禍中に東京神学大学に編入学しました。入学式も中止になりました。大学では、学びを続けるために、可能な限り、良いと示されることを探し求めてきました。早いもので、来年の春には、旅立ちます。すべては、神のくすしき摂理の中にあることだと知ることができます。そして今、主の恵みに委ねられて送り出してくださいと祈っています。
最後となりましたが、ここにお集まりの皆さまの一人一人の心の中に、コロナ後の教会形成について、神の幻、ビジョンが示され、神を信じて、神に従い、神と共に歩み続ける力を与えてくださるよう、主なる神にお祈りさせていただきます。そして、主の慰めと励ましをいただきながら、神の栄光を称える群れとして、さらなる主の恵み深き祝福が、降り注ぎ続けられますよう、お祈りさせていただきます。
(祈り)
父、子、聖霊の三位一体なる神さま。
主の御名を賛美いたします。
神さま、わたしたちは本当に弱い者です。
主の助けがなければ、前に歩(あゆ)み出すことができません。
これまで弱さを抱えながら歩(あゆ)むわたしたちを、
神の御翼の中で見守ってくださったように、
これからもあなたの大いなる愛の中を歩(あゆ)ませてください。
主よ、わたしたちに誇れることがあるとすれば、
十字架の中で生きている日々があることです。
礼拝から礼拝への民として、
御言葉を聞き、あなたの愛を信じて、
歩(あゆ)ませていただいていることです。
主を信頼して歩(あゆ)めるこの信仰生活を感謝いたします。
今わたしたちは、共に御言葉を聞き、
あなたの御前で頭を垂れています。
わたしたちを、幻を見る民として覚えてください。
イエスさまが招かれるとき、
確信を持って、すぐに網を捨てて従う僕とさせてください。
それが荒れ野であっても、茨の道であっても、険しい道のりであっても、
耐え忍ぶ心をわたしたちに与えてください。
白髪になるまで、背負って行こうといわれるあなたを信じ、
共に励ましながら歩み続ける信仰を与えてください。
そして、わたしたちを恵みのよき通り管として用いてください。
再び来られる主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン!
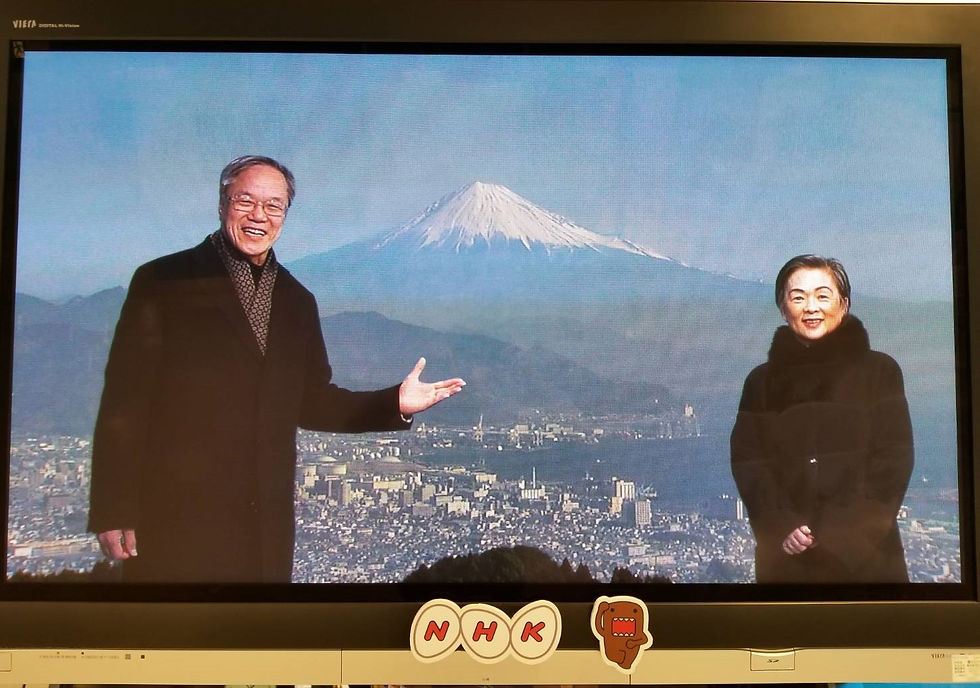
.jpg)

.jpg)
.jpg)









コメント